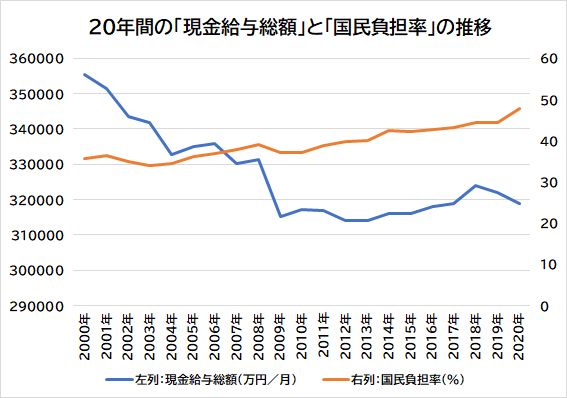昨年も「紅白21を振り返る」を書いたので、今年も。視聴率は21年よりもよかったようだが、それでも40%には届かなかった様子。
大前提として、気づいたことがある。紅白を親戚宅などで酒とともに見て年を越すという方も多かろう。このコンテンツのすごいところは、何と言っても圧倒的に「間が持つ」のである。もし、何も見るものがなかったらと思うと恐ろしい。孫がじいちゃんに「この曲知ってる!」と得意げに教えるのを、じいちゃんが目を細くしながら「全部同じに見えるけど、よく知ってるね」というのが1つの風物詩なのだ。多世代型の選曲なので、とりあえず何らかの歌が引っ掛かるというのがポイント。「へえ、この歌手かわいいね」「懐かしいね、でも声が出てない」とか。何らかのコメントを引き出すことができるという効果があるのだ。これはなかなか他の追随を許さないすごい番組であることがみえてきた。
ーと、これは社会的な観点で分析した紅白像である。確実に日本の年末年始の過ごし方にまだまだ必要なものであるということはみえてきた。みえてきたが、純粋に「番組」としてとらえた時にはどうだったか。
唯一といってよい感動ポイントは、ダチョウ倶楽部と有吉の「白い雲のように」の歌唱シーンである。これは、様々な想いが去来して涙なしでは聞けない名シーンであった。
あとは新年早々、申し訳ないが以下愚痴である。まともに契約した覚えがないのに(結婚して引っ越してすぐ、地上波のときは「受信電波を検知しましたので」とあからさまな嘘を言われたし、BSのときは嫌がる妻を脅して無理やり代筆させて契約するとか無茶苦茶なことをやっているわけです)、安くない受信料を要は無理やり払っているので、この高額番組に愚痴をこぼすくらいは・・・・よいだろう。
まず相変わらず(必ずしも全員が)見ているわけでない朝ドラと大河の宣伝だらけ。一昔前のくだらない「応援合戦」が鳴りを潜めたと思ったら、それがただのCMに変わっただけではないか。そのぶん尺を減らせ、尺を。そもそもが長すぎるんじゃ。
歌だけで何時間も保たないから途中で歌以外のコーナーをはさむのだろうけれど、それだったら2時間くらいのコンパクトバージョンにすればいいのに、という話。
去年は、紅白歌合戦の後半に入る前に「今年も受信料ありがとうございました」と余計なメッセージも入っていた。本心なのか嫌味なのかは知らないが、ただただ「こんな金掛けたセット作るくらいなら値下げしろ」とか、「だったらとっととスクランブルにしろや(払わなくても見られる謎システムがおかしいっちゅうねん)」としか思わず、まともにカネ払ってる側からすると酒が不味くなるったらない。
あと、謎のサッカー推しね。処世術として、そりゃあ、「見たフリ」をして社会でおとなしく過ごしてはいるが、決してあの試合を「全国民が見た」わけではないのだよ。これは五輪にも言えることだが。これだけ価値観が多様化(細分化?)した今、もはや「国民的○○」など存在しない。幻想を無理やり作って意図的にまき散らすのはもうやめてほしい。コロナでも五輪でも一定の「空気」を作るのは大本営発表のころと変わってないって(この国の指導層は明治期から基本的に変わっていないので変わらないのは当たり前だが)。
また別にどうでもいいのだが、似たような「ダンスパフォーマンス」ばかりで、今までで一番「飽き」が強かったのも今回の残念ポイント。別に韓流だろうが何だろうが勝手に好きにすればいいのだが、とにかく途中から全部同じ歌・同じ踊り・同じ顔(←これは嫌味)に見えるという副作用がひどかった(←それは加齢かもしれない)。
・・え?「そんなに嫌なら見るな」ですって? その通り!
これまでずっと、少なくとも30年くらいは「結果発表」まで見て、「蛍の光」を聞いて、カウントダウンして(※最近は「ゆく年くる年」の落ち着きのよさに気づいてきたところだ)、年明けまで起きているみたいに「紅白視聴を習慣化」してきたわたしが、おそらく成人してからはじめて、結果発表前に「あ、もういいかな」と思って早々に床につくくらいには視聴習慣が崩れたのが今回の紅白であった(←それは加齢かもしれない)。
そもそも、最近は妻の実家で親戚と紅白を観ながら(眺めながら)過ごす感じになっているが、初めて自分以外の全員が大トリの「前」で「脱落」(寝落ちではなく、意思を以て就寝に向かうことを指す)し、私は独りでポツンと福山のド派手なスーツを観ながら過ごしたのだ。すごく寂しかったなぁ。そりゃ、「もう結果はいいかな。自分も寝るか」と思って当然なのである。・・と、これくらい、これまでの「視聴習慣」を破壊するのに十分な内容だったわけである。去年の紅白は。否、おととし、去年と続く紅白は、だ。
だいいち、だ。いつも書いている気がするが、このご時世に男女を色分けし、あろうことか「戦わせる」など、普段ポリコレなぞ見向きもしない私ですらちょっと「ウゲゲ」と思い出してくるようになってしまうくらい、因循な価値観が脈々と続いている(であろう)ところが問題だ。これでNHKがゴリゴリの保守なら「まあそういう方針の団体なんだよね」でいちいち目くじら立てるのも野暮だというものだが、一方で「SDGs」を大宣伝(喧伝?)しているNHKさんならば、SDGsの17の目標の5番が「ジェンダーフリーを実現しよう」であることはご存知のはずだ。知っててやっているのだ。
正直、私自身は男が白で女が紅で一向にかまわないのだけれど(「紅一点」という言葉もあるし)、とにかく気持ちが悪いのは一方でSDGsとやらを押し付け、一方で昭和な「男女別模擬戦争」を続けるその矛盾のほうなのだよ。目先のポリコレに囚われて、その矛盾というか、説明のつかないレトリックを「突く」ことを「金主」である視聴者は忘れてはならない。もっと直接的な表現を使うと、結局SDGsはビジネスで言っているだけで、本気で取り組もうとしていない「可能性」が窺えるところを突くべきなのだ(これはSDGsを掲げるすべての企業に突きつけるべき命題でもある)。本当に環境にやさしい状態ならば、いくつもいくつもあるチャンネルの放送を整理するだけで電気代がどれだけ浮くことか。でもそれは絶対にやらないわけでしょう。
・・と、愚痴を書きだしたら止まらないのが今回の紅白であった。私は一体誰と戦っているのだ。「ブラタモリ」とか、私はNHK好きですよ(だからまだテレビを捨てずに受信料を支払っているんですよ)。
しかし、まあ、新たな視点として「話題提供装置」としての紅白の重要性には改めて気づかされる面もあったのは事実だ。「紅白」という枠組みのレーゾンデートルは確かに、ある(ありそうである)。
もっとも、いずれはポリコレの圧に耐えられなくなり、1つは「紅白!歌の祭典!!」とか「紅白年越し歌謡ショー」のように合戦色がなくなる可能性はあるかもしれない。あるいは、合戦色を残すとしても、「紅白東西歌合戦」(メインボーカルの出身地で東西を分ける)とか、「新・紅白歌合戦」(小学校の運動会のように男女混合型)になるかもしれない。
こういうことを妄想しながら、時はいたずらに過ぎていくのであった。
2023年1月2日